「補助金を使ってスマホを買いたいのですが、可能ですか?」
これは補助金相談を受けていると、驚くほど多く寄せられる質問です。特に、個人事業主やフリーランス、副業を始めた方、学生起業家などから頻繁に耳にします。
一見すると「業務に使うからスマホも立派な投資では?」と思われがちですが、結論から言うと IT導入補助金や業務改善助成金でスマホを購入することはできません。
本記事では、
- なぜ補助金でスマホが対象外になるのか
- 公式要領に明記されている「対象外の根拠」
- 代わりにどんな投資なら補助対象になるのか
を5つの理由と具体例をもとに整理し、最後に「賢い補助金活用の道筋」をご紹介します。初めて補助金に取り組む方でも理解しやすいように、実際の事例や準備のコツも交えて説明しますので、ぜひ参考にしてください。
- 補助金の概要
- 対象となる事業者
- 個人事業主も対象になるのか
- 実際の採択事例
- 補助対象となる経費
- IT導入補助金で対象になる経費
- なぜ「補助金でスマホは買える」と誤解されやすいのか
- 「業務用=対象」と短絡的に考えてしまう構造
- スマホが補助対象にならない5つの理由
- スマホを「間接的に業務で活用する」方法
- まとめ
補助金の概要
補助金とは何か
補助金とは、国や自治体が企業や個人事業主に対して交付する「返済不要の資金援助」です。銀行融資のように返す必要がないため、資金繰りの強力なサポートとなります。
ただし、「誰でも必ず受け取れるお金」ではなく、明確な目的に沿った事業計画を提出し、審査を通過した場合にのみ採択されます。つまり、事業の将来性や社会的意義を伝えることが重要です。
注意ポイント:時折「スマホを買ったのですが、補助金を貰えるのですか」という問合せがあります。明確な事業目的がないまま、計画書も申請せず購入した場合スマホに限らず原則的には全て対象外です。
補助金の役割とメリット
補助金の目的は、中小企業の成長や地域経済の活性化を後押しすることです。たとえば、新しい設備を導入する、販路を開拓する、ITを活用して業務効率を上げる――といった取り組みが支援対象となります。
メリットは以下のとおりです。
- 自己負担を減らし、挑戦のハードルを下げられる
- 計画的に事業を見直すきっかけになる
- 採択されれば信用力が増し、金融機関からの評価も高まる
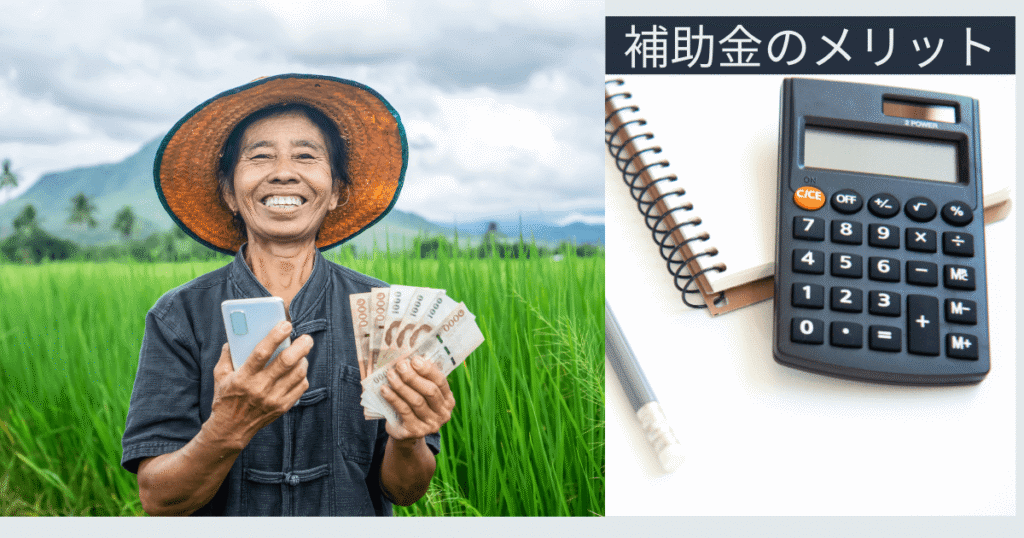
補助金の注意点
一方で注意も必要です。補助金は後払いが原則であり、まずは自己資金や借入で支出を行い、後から補助金が入る仕組みです。
また、申請に時間と手間がかかるため、余裕を持って準備する必要があります。さらに、採択後も実績報告や証憑管理など、事務作業が求められます。
対象となる事業者
中小企業・小規模事業者の定義
補助金の多くは「中小企業基本法」に基づき、資本金や従業員数で対象範囲が決められています。
たとえば製造業であれば資本金3億円以下、または従業員300人以下が目安です。小売業やサービス業の場合はさらに基準が小さく、資本金5,000万円以下・従業員50人以下が対象となります。
つまり、大企業ではなく「地域で事業を営む中小企業・個人事業主」を想定して設計されている制度です。
個人事業主も対象になるのか
「法人でなければ補助金は受けられないのでは?」と心配する方もいますが、多くの補助金は個人事業主も対象に含まれます。
実際、美容室や飲食店、建設業の一人親方など、個人事業の形態で申請・採択された事例は数多くあります。重要なのは「事業として継続性があるか」「売上拡大や生産性向上につながるか」という点です。
業種ごとの特徴と留意点
業種によっては、補助金の対象外となるケースもあります。たとえば、風営法に基づく一部の業種や、政治・宗教活動を主目的とする事業は支援を受けられません。
また、建設業や運送業などの規制業種では、許可や登録の有無が審査でチェックされるため、申請前に自社の法的要件を確認しておく必要があります。
実際の採択事例
実際に採択された事例を見ると、
- 飲食店がテイクアウト用の設備を導入
- 美容室がウェブ予約システムを導入し、新規顧客を増やした
- 製造業が新しい機械を導入し、生産性を向上させた
といった取り組みがあります。
いずれも「売上拡大」や「業務効率化」という補助金の目的に合致しているのが共通点です。
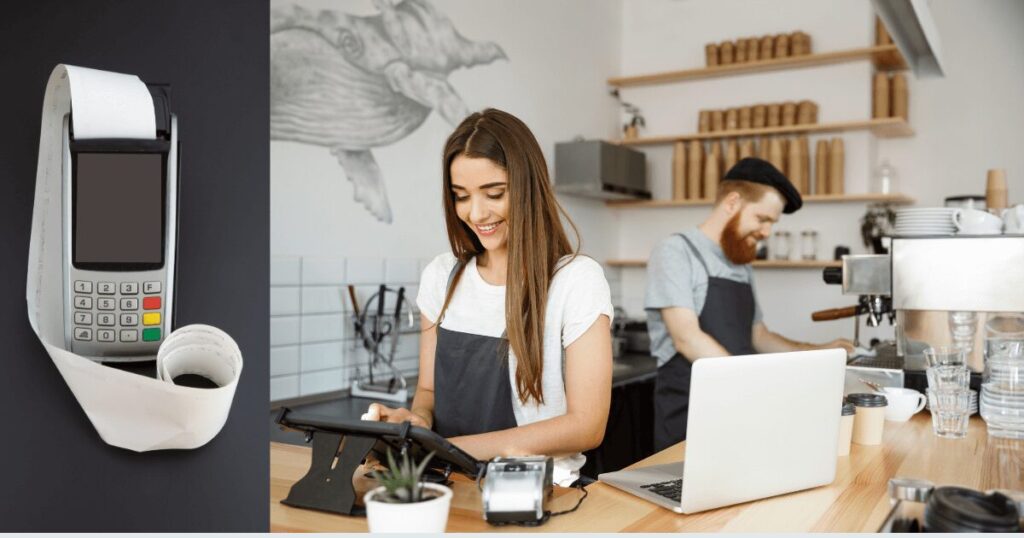
補助対象となる経費
補助対象の基本原則
補助金では「事業の成長や業務改善に直接役立つ費用」が対象になります。
具体的には、以下の条件を満たす経費が基本です。
- 事業遂行に必要であること
- 購入や契約が明確に証明できること(領収書や契約書など)
- 補助金の趣旨に沿った投資であること
補助対象であれば、費用の一部が補助金として支給されます。逆に、プライベートや趣味に関わる費用は対象外です。
IT導入補助金で対象になる経費
IT導入補助金の場合、対象経費は大きく分けて以下の通りです。
- ソフトウェア費用
クラウド会計ソフトや顧客管理システムの導入費用、ライセンス費用など。 - 役務費
導入サポートや研修、設定代行などのサービス費用。 - ハードウェア(限定的)
原則ハードウェアは対象外ですが、ソフトウェアの利用に不可欠な場合(例:POSレジ一体型端末)に限り認められるケースがあります。
注意ポイント:スマホやタブレット単体の購入は対象外です。
業務改善助成金で対象になる経費
業務改善助成金は「労働環境改善」「生産性向上」に直結する設備やシステムが対象です。具体例は以下の通りです。
- 勤怠管理システム導入費
- キャッシュレス決済端末や自動釣銭機
- 省力化設備や作業効率化ツール
ポイント:スマホや汎用PCは対象外です。あくまで「業務改善効果が数字で示せる設備」が補助対象になります。

注意したい経費の分類
補助金の申請では、経費の分類を誤ると不採択や後から返還要求につながる可能性があります。
- 対象経費:システム導入費、設備購入費、研修費
- 対象外経費:スマホ、汎用PC、日用品、消耗品、光熱費、交通費(原則)
例:業務改善助成金で勤怠管理システムを導入しても、社員が使うスマホ端末費用は含まれません。
実務での注意点
- 領収書の管理:補助金交付後も提出が必要な場合があります。
- 事前相談の活用:事前に補助金窓口や専門家に確認すると、対象外経費を誤って計上するリスクを減らせます。
- システムとのセット購入:ハードウェア購入が補助対象になるかどうかは、ソフトウェアや設備とセットで検討すると良いでしょう。
なぜ「補助金でスマホは買える」と誤解されやすいのか
スマホは業務利用度が高いから
現在、ビジネスにおけるスマホの利用率は非常に高く、総務省の通信利用動向調査(2024年版)によれば、個人事業主の約7割がスマホを業務活用しています。
例えば:
- 顧客とのLINEやメール対応
- クラウド会計アプリへの入力
- モバイル決済やQRコード決済
このような実務が増えているため、「業務で使う=補助金対象では?」と考えられてしまうのです。
副業・フリーランス層に特に多い誤解
副業や個人フリーランスの場合、事務所を持たずにカフェや自宅で作業する人が多数派です。そのため「唯一の業務機材=スマホ」というケースも少なくありません。
Google検索でも「スマホ 補助金」「フリーランス 補助金 スマホ」といったクエリが見られ、誤解が需要を生んでいることが分かります。
「業務用=対象」と短絡的に考えてしまう構造
補助金の説明会やパンフレットには「業務効率化に資する投資が対象」と記載されていることが多く、一般の方には「なら業務で使うスマホもOK」と思われてしまいます。
しかし実際には、補助金には**対象要件(IT導入補助金なら登録ITツール、業務改善助成金なら労働環境改善に直結する設備)**が細かく定められており、スマホは対象外とされています。
スマホが補助対象にならない5つの理由
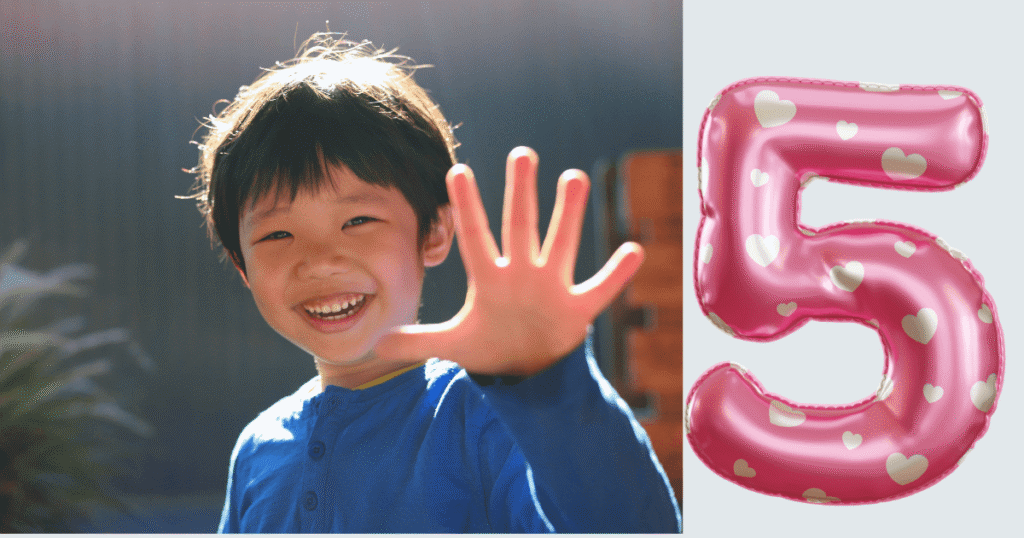
理由① IT導入補助金は「登録ITツール」のみ対象だから
IT導入補助金の仕組み(登録ITツール制度)
IT導入補助金では、「IT導入支援事業者」が事前に登録した ソフトウェアやクラウドサービス だけが補助対象となります。
つまり、申請者が自由に選んだツールや機材は対象外であり、スマホのようなハードウェアはそもそも登録されません。
公式要領の引用例(2025年IT導入補助金公募要領より):
「補助対象となるITツールは、事前に登録されたソフトウェア・クラウドサービス・関連するオプション及び役務である。」
スマホは「ハードウェア」で登録されない
スマホはソフトウェアではなく「ハードウェア機器」であり、登録リストに入る余地がありません。
また「クラウドサービスを利用するための端末」として必要でも、スマホ自体は補助対象から外れるルールになっています。
補助対象になる例:会計ソフトやクラウドシステム
逆に、IT導入補助金で対象となる投資の具体例は次のとおりです。
- クラウド会計ソフト(freee、マネーフォワード)
- 顧客管理システム(Salesforceなど)
- 予約管理システム(美容室やサロン向け)
これらは「登録ITツール」として事業成長につながると認められるため、補助金対象になります。
FAQ:
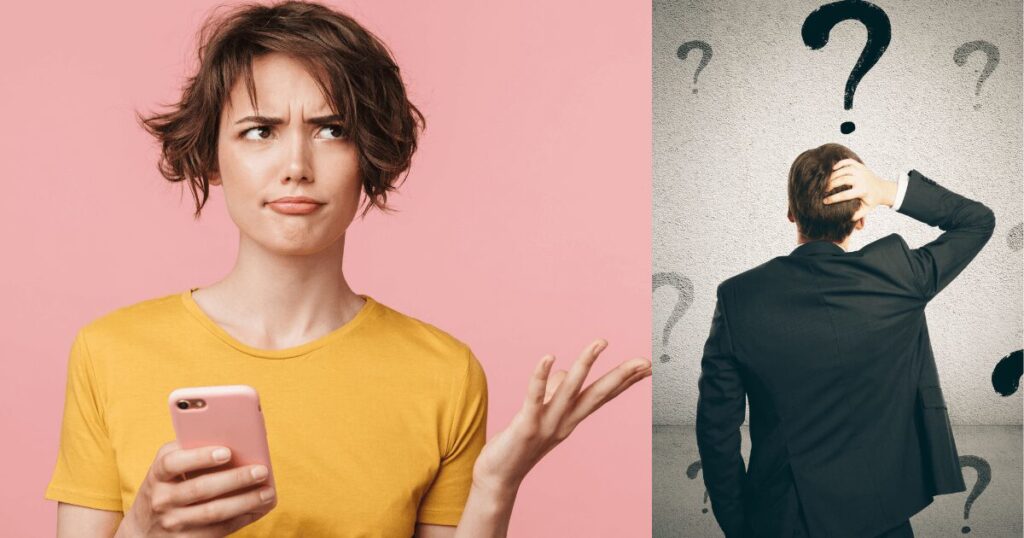
理由② 業務改善助成金では「汎用機器は補助対象外」と明記されている
公式要領にある対象外リスト(PC・スマホ・タブレット)
業務改善助成金の公募要領には、はっきりと「補助対象外」として パソコン、スマートフォン、タブレット端末 が記載されています。
これは「誰でも利用する汎用機器」であり、業務改善の効果が直接測定できないためです。
なぜ対象外にされているのか(労働環境改善効果が不明確)
業務改善助成金は「労働時間短縮や生産性向上」を目的としており、例えば:
- 勤怠管理システム導入 → 労務管理の効率化
- POSレジ導入 → 会計作業の時間削減
といった「労働環境改善が明確なもの」が対象です。
一方、スマホは用途が多岐にわたり、業務改善効果が具体的に示しづらいため、対象外になっています。

補助対象になる例:POSレジや勤怠管理システム
代わりに業務改善助成金で補助されやすい設備の例は以下の通りです。
- タイムカード連動のIC勤怠管理システム
- キャッシュレス決済端末
- 自動釣銭機付きレジ
これらは「労働生産性指標の改善」を証明しやすいため、助成金の趣旨に合致します。
FAQ:
理由③ 個人利用と業務利用の切り分けが困難だから
スマホは私用・業務の両用が当たり前
スマホは仕事でもプライベートでも使う道具です。
例えば、同じ1台で「顧客対応の電話」と「友人とのLINE」を行うのが普通ですよね。
補助金は「事業のための投資」に限定されるため、私用と混在するスマホは線引きが難しいのです。
審査で「業務専用利用」を説明できないリスク
もし補助金を使ってスマホを購入したとしても、審査で「これは業務専用です」と説明するのは困難です。
さらに、審査担当者に「プライベート利用しているのでは?」と疑われると、不採択や返還につながります。

監査で返還を求められる可能性
補助金は交付後も監査が入ることがあります。そこで「実は私用でも使っていた」と判断されれば、補助金を返還しなければなりません。
リスクが大きいため、スマホは最初から対象外とされているのです。
FAQ:
理由④ 減価償却資産の扱いと補助金の整合性
補助金は「長く使う資産」への投資を想定
補助金は、パソコンやシステム、設備など「数年単位で使い続けるもの」に出されるのが基本です。
理由は、国が「投資効果を長く発揮してほしい」と考えているからです。
スマホは消耗品的扱いで買い替えが早い
スマホは2〜3年で買い替える人がほとんどです。
減価償却上も耐用年数は短く、政策的に「長期的な生産性向上」に結びつけにくいとされています。
政策効果の測定が難しい
仮に「スマホを導入したから売上が伸びた」と言っても、それがスマホのおかげなのか、他の要因なのかを証明するのは難しいですよね。
こうした理由から、国としては「スマホ=補助対象外」としています。
理由⑤ 政策目的(生産性向上・雇用創出)に合致しないから
補助金は「事業成長・雇用改善」を目的にしている
IT導入補助金も業務改善助成金も、「事業者の売上アップ」「働き方改革による労働環境改善」といった政策目的があります。

スマホ単体購入では効果を示せない
スマホ自体は便利なツールですが、単体で導入しても「生産性が何%向上した」と説明するのは難しいです。
審査基準との整合性が取れない
補助金の審査では「どんな効果があるか」を数値で示す必要があります。
「スマホを買ったら便利になりました」では説得力が弱く、採択されないのです。
代替案:スマホはダメでも、こんな投資なら補助対象になる
IT導入補助金で対象になる投資例
- クラウド会計ソフト(例:freee、マネーフォワード)
- 顧客管理システム(CRM)
- 予約・決済のオンラインシステム
👉 これらはスマホから操作できますが、補助対象は「システム利用料や導入費用」です。
業務改善助成金で対象になる投資例
- 勤怠管理システム+ICカードリーダー
- キャッシュレス決済端末
- 自動釣銭機付きレジ
👉 「労働時間短縮」や「業務効率化」が明確に説明できるものは対象になりやすいです。

スマホを「間接的に業務で活用する」方法
補助金で買えなくても、スマホを業務で使う方法はあります。
- 導入したクラウドシステムをスマホで操作する
- 勤怠管理アプリを従業員がスマホで打刻する
- 顧客管理システムに外出先からアクセスする
つまり「スマホ本体は対象外」でも「スマホで利用できる業務システム」は補助金の対象になり得るのです。
まとめ
補助金でスマホが買えない理由の総括
ここまでの内容を振り返ると、スマホが補助対象外とされる理由は次の5つでした。
- IT導入補助金は登録ITツールのみ対象
- 業務改善助成金は汎用機器を対象外と明記
- 業務利用と私用の切り分けが困難
- 短期間で買い替えが必要な資産である
- 政策目的に合致しない
制度を理解すれば有効な活用が可能
補助金は「何がダメか」を知ることと同じくらい「何なら使えるか」を知ることが重要です。
スマホは対象外ですが、クラウドサービスや労務管理システムなどはしっかり補助対象になります。
補助金で困った時は専門家へ
「自分の事業の場合、どんな投資なら対象になるのか?」
「このシステム導入は補助金を使えるのか?」
そうした疑問がある方は、ぜひ専門家に相談してください。

私たちは補助金制度の最新情報を押さえ、採択につながる提案を行っています。
👉 お問い合わせはこちらからどうぞ。

